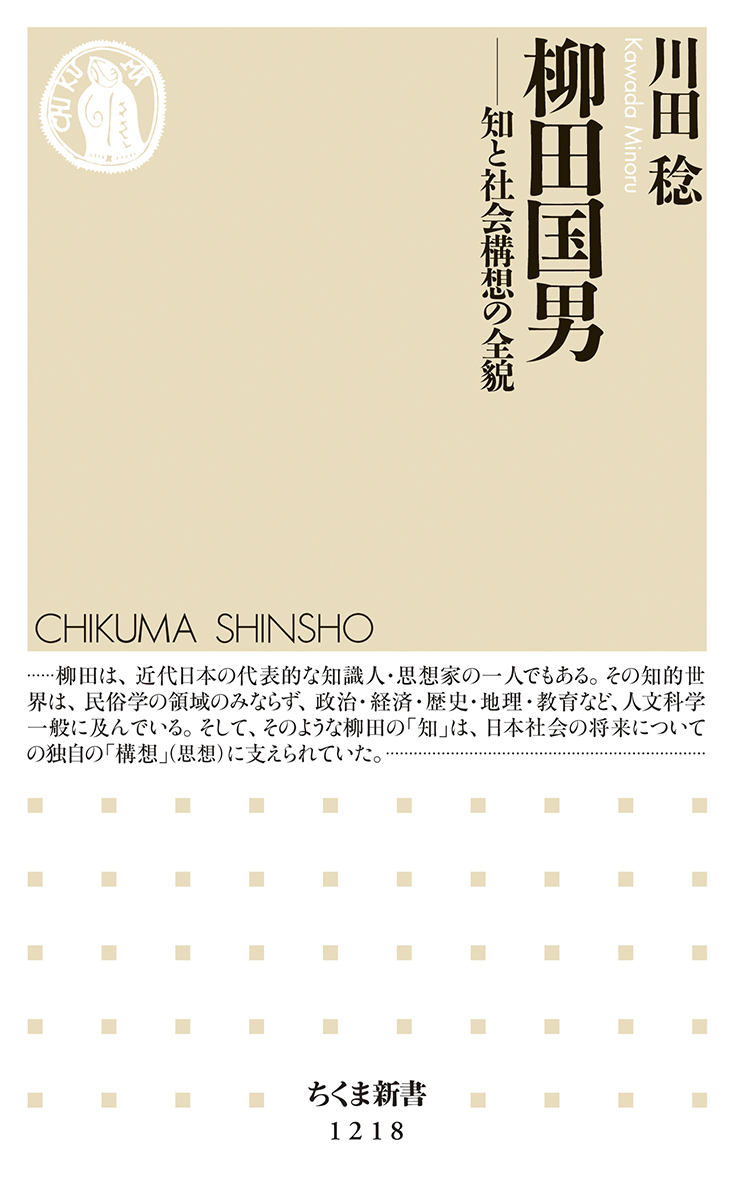
柳田国男 知と社会構想の全貌
川田稔 著
ちくま新書1218
2016年11月10日 第1刷発行
序章 足跡と知の槪観
渡欧が柳田にとって大きな転機となる。
ヨーロッパ滞在中に柳田はジュネーブ大学の講義を聴講するとともに、ヨーロッパ各地を訪れている。そこで当時の欧米人文社会科学の最先端の学問と本格的に接触する。ことに、マリノフスキー、ボアズ、リヴァースらの新しい文化人類学・民族学の流れや、デュルケーム、レヴィ=ブリュル、モースらのデュルケーム学派から大きな刺激を受ける。このことは柳田のそれまでの学問に大きな飛躍をもたらすことになる。
ヨーロッパにおいて新しい知的インパクトを受け、それまでの自分の学問を、新たな方法でもう一度立て直そうとするのである。それがいわゆる柳田民俗学となっていく。
ヨーロッパ・フォークロアは、ことさら珍奇な習俗に関心を向けており、資料が断片的で量的に乏しく、方法的にもそれらによる制約を受けていた。また19世紀末までの人類学は世界各地の断片的で不確かな情報によっており、資料的根拠や論証手続の上で欠陥の多いものだった。主に宣教師や植民地行政官の報告書、商人や探検家の旅行記などを資料としていたからである。
それに対して20世紀に入ってからの人類学は、現地語を習得した専門の研究者が周到な現地調査を積み重ねる方法を採用することになる。その調査結果を資料的な基礎として住民の社会や生活文化全体を体系的に把握する研究を進めていた。厳密な学問的方法論に基づくものに大きく性格を変えていたのである(その代表的成果が、マリノフスキー 『西太平洋の遠洋航海者』)
第一章 初期の農政論
明治期日本の農政学の3つの潮流
・フェスカ、横井時敬、酒匂常明らの駒場農学校系(ドイツ系)
・エッゲルト、松崎、柳田、河上、石黒忠篤らの東京帝国大学法科大学系(ドイツ系)
・クラーク、内村鑑三、新渡戸稲造らの札幌農学校系(アメリカ系)
第二章 日本的近代化の問題性 危機認識
第三章 構想Ⅰ 地域論と社会経済構想
第四章 構想Ⅱ 政治構想
第五章 自立と共同性の問題
第六章 初期の民間伝承研究から柳田民俗学へ
第七章 知的世界の核心Ⅰ 日本的心性の原像を求めて
近代天皇制の問題を考える場合、
・天皇を国家統治の大権を持つものとして現実の政治権力をそこに 根拠をづけようとする考え方
・それをむしろ非政治的な象徴的なものにしていこうとする考え方
前者の考え方はドイツの政治システムをモデルとしたものであり、後者はイギリスをモデルとしている。
マックス・ウェーバーは君主制論の観点から、前者を「立憲制的君主制」、後者を「議会制的君主制」と呼んでいる。
第八章 知的世界の核心Ⅱ 生活文化の構造
柳田は『郷土生活の研究法』で民俗資料を次のような項目に分類している。
・有形文化[生活外形]
・言語芸術[生活解説]
・心意現象[生活意識]
終章 宗教と倫理