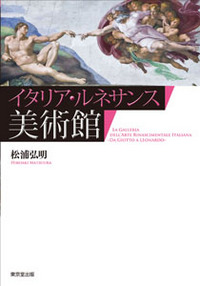
イタリア・ルネサンス美術館
松浦弘明 著
東京堂出版 発行
2011年11月30日 初版発行
この本では、ルネサンス期の作品による、架空の美術館を設定しています。これにより作品の比較を容易に行えるようにし、よりわかりやすく解説しています。

ユリウス2世在位8年目の1511年に完成したこの作品。
アテネの学堂というタイトルは17世紀末につけられたものに過ぎない。
著名な哲学者や学者が描かれているが、キリスト教以前の異教の人々である。
この作品より約150年前に描かれた、フィレンツエはサンタ・マリア・ノヴェッラ聖堂内に描かれた「トマス・アクィナスへの礼賛」と呼ばれる壁画。
左下のピュタゴラスのグループは算術を表す
音楽は?左下のぶどうの葉の冠をかぶった男ではないか?
快楽主義者の哲学者エピキュロスとか、オルフェウス教の祭司だとかという説がある。
その上方の壁に竪琴を抱えた音楽の神アポロの像が設置されているのは偶然ではない。
下のグループが4科を象徴するのでは、上のグループは3科を表すのではないか?
中央の二人が議論していることから「論理学」と考えられ、
左端の巻物を持っている少年やソクラテス、巻物は「修辞学」の伝統的な持ち物であるから、左側のグループは「修辞学」のグループ
右側は「文法」のグループとなる。大地を指差す(もっとも基本的な科目を示唆する)老人やその後ろの子供に読み書きを教える女性のレリーフなどからそういえるのではないか。
まとめると
修辞学 論理学 文法
という配置
登場人物の古代の学者たちが追い求めているのは「真理のありか」
つまり「論理的真理」の探究
つまり人間が論理的な観察や考察によって、いかに真理に迫ることができるかを、ラファエロは描こうとした。
「アテネの学堂」の最重要課題は?
「トマス・アクィナスの礼賛」のような象徴的・記号的な表現ではなく
より自然にイリュージョニスティックな形で自由学芸を描くこと
そのために舞台として
線遠近法と陰影法を巧みに使い、画面の中に入り込めそうな絵画空間を作り出す。そして
基本的な3科と専門的な4科の分類のため、階段を使って性質の異なる二つの空間を創り出した。
そしてグループ間のつながりのため
間に人物を配したり
手の動きや視線の向きを工夫したりした。
アテネの学堂がイリュージョニスティックな表現の頂点
それ以前で、イリュージョン性を備えた作品は、ダヴィンチの「最後の晩餐」以外には無い。
