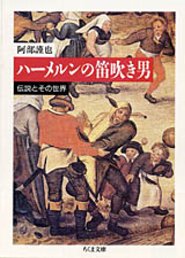
伝説とその世界
阿部謹也 著
2010年11月20日 第28刷発行
三点の中世史料から
という事実が確認できる。
12、3世紀はヨーロッパにおいて都市の台頭期であり、市民の活力はあふれ、生産力は増大し、いわば「開かれた世界」の相貌を呈していた。
しかし13世紀の末になると、領邦国家の形成とあいまって、こうした庶民の活力に上から「ひとつの型」が定められていく。法制や社会聖堂の整備、市壁や建物の立派さという外面的繁栄の陰で呻吟していた多くの庶民がいた。
ハーメルンにおいては、1277年の特許状における「1年と6週間市内に留まったものは自由とする」という法規定が、それ以前からハーメルン市内に先祖代々住んでいる隷属民に対しては、少なくとも通用しなかった。
ハーメルンの子供たちの失踪は1284年であった。この時期には東ドイツ植民、それも農民の移住が盛んに行われた。それゆえこの失踪を「東ドイツ植民」(ヴァン説)として、あるいは家系学との関連から「植民途中での遭難」(ドバーティン説)と関連付けた説もある。
しかしこの話の悲劇的な雰囲気は、何らかの不測の事故を予測させるものと考え、東ドイツ植民のような計画的な行動がこの事件の背景とはみられないという見方をする。
そこでヨハネ祭の日に、夏至の火を町から2マイルほど離れたポッペンブルグの崖の上に灯す習慣があったことから、子供たちは大勢で祭りの興奮のあまりこの火をつけに出かけ、その湿地帯にある底なし沼にはまり込んで、脱出できなくなった、との説(ヴォエラー説)もある。
当時の下層民の日常生活と、祭りのときの解放の姿を考えると、祭りの興奮が子供たちにもうつった可能性が一番高いように思える。
また中世においては、「笛吹き男」の属する遍歴芸人の階層が、教会や社会から差別された賤民であり、悪行の象徴としてあらゆる不幸な事件の責任を転嫁されていたという点を指摘している。
伝説というのは庶民の間で語り伝えていったものである。
しかしひとたび知識階層に属する人間が書きとめ、評釈を加えるようになると、そうした行為が庶民の口伝に影響を与える。
庶民の宗教的教化や精神的訓育の手段とされるようになると、本来の伝説はその姿をまったく変えて現れることとなる。
市当局と教会はハーメルンの一般市民が1551~1553年の災害に恐れおののいていることを利用し、「笛吹き男伝説」を彼らの権威を裏づけ、庶民を教導するための手段としようとした。
そこで市の新門にラテン語の碑文を掘り込ませた。
「1556年
すなわちマグスが130人の子供を町から
奪っていってから272年のち、この門は建立された」
ここでは笛吹き男はマグス(神秘的な隠れた世界の支配者)として示されている。
この失踪伝説に「鼠取り男伝説」がはじめて登場するのは、1565年頃に書かれた「チンメルン伯年代記」である。
鼠取り男の伝説は、鼠の害に苦しむヨーロッパでは多く見られた。そしてハーメルンも水車の町として鼠の格好の棲みかである穀倉も多く、鼠の害に苦しんでいた。
そして各地の「鼠捕り伝説」も「130人の子供の失踪伝説」にも「笛吹き男」がいるという事実がある。
笛吹き男という名を耳にしたとき、当時の人々は直ちに遍歴して歩く放浪者、そして鼠捕り男などのことを思い出した。両者の社会的地位は同一だったのである。
そのような中で古い伝説は、鼠捕り男と市参事会の裏切りの伝説へと転化していった。突如として政治的に鋭い輪郭をもって現れ、うちつづく自然的・人為的災害に対する庶民の怨念が表現された。
16、7世紀以来「ハーメルンの笛吹き男」伝説は
教会や神学者による民衆教化としての手段
不可解な運命に弄ばれてきたドイツ民族の過去の解明の一手段
解放戦争、ドイツ統一運動へ民衆を結集する手段
民衆精神の発露
単なる歴史的好奇心
知識人が民衆伝説をとらえようとする場合、どうしても知識人の社会的立場が影を投げる。
歴史的分析を史実の探索という方向で精緻に行えば行うほど、伝説はその固有の生命を失う。
伝説を民衆精神の発露として讃えれば政治的に利用されてしまい
課題意識や使命感に燃えて伝説研究を行えば民衆教化の道具となり、はてはピエロとなる。
ハインリッヒ・シュパヌートは78歳で「ハーメルンの鼠捕り男―古伝説の成立と意味」なる学位論文を出して博士となった。
知識人であったが、知識人としての特権をほとんど享受することなく、単に自分の情熱を注ぐ対象との緊張関係の中で過ごした。これは大変幸せな人生であったといえよう。